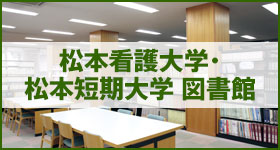教育に関する情報介護福祉学科
教育目標
介護福祉学科では、本学の建学の精神、2学科の教育理念・教育目標より、以下の教育目標を掲げています。
- 豊かな感性を備え、人への深い関心をもち、個人の尊厳を守り、信頼関係を築くことができる人間教育を行う。
- 社会的期待に応えることができるよう介護福祉の倫理のもと、介護福祉の専門的知識と技術を修得し、さまざまな課題を解決できる力を養う。
- 地域に開かれ地域に密着した教育を行い、広い視野に立って多職種との連携・協働を考えることのできる力を養う。
アドミッション・ポリシー<AP>(入学者受入れの方針)
本学は「豊かな人間性の涵養」と「ケアスペシャリストの育成」を教育理念としています。それに基づき、豊かな感性を備え人と関わり、専門的知識・技術を身につけて、地域社会に貢献できる学生を求めます。
(1)介護福祉や社会福祉に関心をもち学ぶ意欲をもっている。
(2)人の立場になって考えることができる。
(3)人の話をよく聴き、自分の考えを伝えることができる。
(4)人とともに協力して活動に取り組むことができる。
(5)入学後の学修に必要な基礎学力がある。
ディプロマ・ポリシー<DP>(学位授与の方針)
本学科に2年以上在学し、本学の「建学の精神」「教育理念」「教育目標」に基づいて設定した学科の授業科目を履修し、規定する必要単位を修得した学生は、次の到達目標に達した人材であると認定し、「短期大学士」の学位を授与します。
- 温かいこころと豊かな感性を備え、人への深い関心をもち、個人の尊厳を守り、信頼関係を築くことができている。
- 介護を必要とする人の自立支援と、地域におけるその人らしい生活を支えることのできる専門的知識と技術を修得している。
- 根拠に基づいた介護過程の展開ができ、質の高い利用者本位のサービスを考えることができている。
- 常に問題意識をもち、介護実践の質的な向上や介護をめぐる課題について探求し、より良い介護を追求できている。
- 多職種や地域住民との連携・協働の必要性を理解できている。
建学の精神と到達目標の関係
建学の精神
- 人道主義:ひとと交わり、ひとを育て、ひとに誠意を尽くす人間性の涵養
- 自己研鑽の精神:自立した専門職業人の育成
教育理念
- 保育士および幼稚園教諭・介護福祉士として、「命・可能性・権利を保障し、その人らしい生活を支えるケアスペシャリスト」の育成
- 地域の保健医療福祉および教育に貢献できる人材の育成
教育目標
- ケアスペシャリストとしての人間性と倫理観の育成
- ケアスペシャリストに必要な専門的知識・技術・思考能力の育成
- 地域における保健医療福祉及び教育の多様化・個別化するニーズに応える実践能力の育成
<ケアスペシャリストの育成の5つの柱>- ひとの命と健康を考える
- ひとの可能性を考える
- ひとの生活を考える
- ひとの権利を考える
- 学修の基礎力を培う
介護福祉学科 教育目標
- 豊かな感性を備え、人への深い関心をもち、個人の尊厳を守り、信頼関係を築くことができる人間教育を行う。
- 社会的期待に応えることができるよう介護福祉の倫理のもと、介護福祉の専門的知識と技術を修得し、さまざまな課題を解決できる力を養う。
- 地域に開かれ地域に密着した教育を行い、広い視野に立って多職種との連携・協働を考えることのできる力を養う。
介護福祉学科ディプロマ・ポリシー
- 温かいこころと豊かな感性を備え、人への深い関心をもち、個人の尊厳を守り、信頼関係を築くことができている。
- 介護を必要とする人の自立支援と、地域におけるその人らしい生活を支えることのできる専門的知識と技術を修得している。
- 根拠に基づいた介護過程の展開ができ、質の高い利用者本位のサービスを考えることができている。
- 常に問題意識をもち、介護実践の質的な向上や介護をめぐる課題について探求し、より良い介護を追求できている。
- 多職種や地域住民との連携・協働の必要性を理解できている。
カリキュラム・ポリシー
カリキュラムは、「教養科目」と領域「人間と社会」「介護」「こころとからだのしくみ」「医療的ケア」で編成し、これらを2年間に配当しています。
「教養科目」は、専門職としての価値・知識・技術をもって、成長し続ける力を養うための土台作りの科目として編成されています。特に豊かな人間性を育むこと、短期大学での学び方の基礎を身につけること、進路設計・進路選択を考えることを重視しています。
領域「人間と社会」「介護」「こころとからだのしくみ」「医療的ケア」は、介護福祉士国家試験受験資格に関わる専門科目から構成されています。
- 感性や表現力を高め、豊かな人間性を培うため、人間の尊厳や発達、人間関係、コミュニケーションについて複数の科目で段階的・横断的に学ぶことができる科目構成としている。
- 介護福祉に関する専門的知識・技術を身につけ、その人らしい生活や自立支援を図ることができる力を培うため、「教養科目」と領域「人間と社会」「介護」「こころとからだのしくみ」「医療的ケア」に属する各科目について相互に関連づけながら段階的に学ぶことができる科目構成としている。
- 根拠に基づく利用者本位のサービスを検討するため、生活支援技術と介護過程と介護実習を中心に各科目で修得した知識・技術を統合して介護過程を展開する能力を段階的に培うことができる科目構成としている。
- 探求心や課題解決力の基礎となる研究的態度を養うため、各科目で修得した専門的知識・技術や介護実習で得た学びを総合的に活用し、2年間の総まとめとして介護福祉研究に取り組む科目構成としている。
- 地域における生活支援実践力を高められるよう、多職種との連携や地域の理解について複数の科目と介護実習で段階的・横断的に学ぶことができる科目構成としている。
学習成果
介護福祉学科では、2年間の学びを通して、以下の学習成果を定めています。
(1)豊かな感性と表現力を備え、相手にもわかりやすく伝えることができる。
(2)相手の立場になって考え、円滑な人間関係の形成につながるコミュニケーション能力を身につける。
(3)その人らしい生活や自立支援を多面的に検討するため、幅広い教養に加え、介護福祉に関する専門的知識を身につける。
(4)その人らしい生活や自立支援につなげるため、介護福祉に関する専門的技術を身につける。
(5)根拠に基づいたサービスを検討するため、介護過程に関する知識を身につける。
(6)利用者本位のサービスにつなげるため、介護過程を実際に展開することができる。
(7)自らの問題意識に基づき課題を設定する中で探究心を養うことができる。
(8)課題の解決に向けて、適切な方法で取り組み、その結果を考察する過程を通して、課題解決力の基礎となる研究的態度を身につける。
(9)授業や介護実習を通して多職種連携・協働を理解し、チームワークを発揮できる能力を身につける。
(10)地域の人々との交流を通して地域の文化・歴史を把握し、地域に貢献する意義を理解することができる。

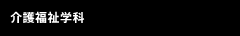 介護福祉学科
介護福祉学科